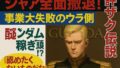この記事は約 4 分で読めます。
【追記】下段に追記を記載しています。
気象庁は本日、地球規模で進行する温暖化現象とそれに伴う気候変動を受け、日本の季節区分を従来の「四季」から「六季」へと変更することを発表した。明治時代に気象庁が発足して以来、日本の季節区分が変更されるのはこれが初めて。来年度から適用される予定で、教科書やカレンダーにも大きな影響が出そうだ。
四季では捉えきれない「現代の気候」
今回の改定の背景にあるのは、年々曖昧になる「季節の変わり目」だ。気象庁の分析によると、春と夏、夏と秋の移行期間が顕著に長くなり、「春なのに夏日」「秋なのに真夏日」といった現象が常態化している。
気象庁の担当者は記者会見で、「これまでの『春夏秋冬』という大まかな区分では、もはや国民生活の実態に合わないと判断した。特に近年、春の陽気から一気に夏日が続く『初夏』や、夏の猛暑が長引いた後に訪れる『晩夏』といった、中間的な季節が明確に観察されるようになった」と語った。この2つの季節を独立させることで、より正確な気象情報を提供できるとしている。
新たな季節の定義:衣替えや行事にも影響か
新たに追加されたのは、「初夏」と「晩夏」の二つの季節。これにより、日本の季節は以下の六つとなる。
- 春(3月~4月): 従来の春とほぼ同じ。新年度が始まり、桜が咲き誇る。
- 初夏(5月~6月): 陽気が一気に高まり、真夏日が増え始める時期。ゴールデンウィーク明けから梅雨入りまでが該当する。
- 夏(7月~8月中旬): 猛暑のピーク。ゲリラ豪雨や熱波が頻発する、真の夏。
- 晩夏(8月下旬~9月): 猛暑が和らぎ始めるものの、残暑が厳しい時期。お盆を過ぎても気温が下がらず、秋の気配が感じにくい期間。
- 秋(10月~11月): 従来の秋とほぼ同じ。紅葉が始まり、過ごしやすい気候が続く。
- 冬(12月~2月): 従来の冬とほぼ同じ。寒さが厳しく、雪が降る時期。
この変更は、私たちの生活に具体的な影響を与えそうだ。例えば、学校の夏休みは「夏」と「晩夏」に分かれ、冬服への衣替えは「秋」が始まってから、といったように、慣れ親しんだ生活習慣の見直しが迫られる。
戸惑う人々、そして新たな季語の誕生
この突然の発表に、国民からは困惑の声も上がっている。
「秋は3ヶ月だと思っていたのに、10月からしか始まらないなんて…。なんだか秋が短くなったみたいで寂しい」と語る30代女性。「『初夏の候』とか『晩夏の候』とか、新しい季語を覚えなきゃいけないの?手紙を書くのが大変になる」と嘆く声も聞かれた。
一方、気象予報士たちは「より細分化された予報が可能になる」と歓迎の意向を示している。さらに、俳句の世界では「初夏」「晩夏」という新しい季語が誕生する可能性もあり、文豪たちが頭を悩ませる日も近いかもしれない。
この前代未聞の季節改定が、私たちの生活にどのような影響を与えるのか。夏休みの日程、衣替えのタイミング、そして何より季節を感じる心そのものに、大きな変化を迫ることになりそうだ。
■追記(事実報):2025/10/30追記
三重大学 生物資源学部 立花教授らによる春秋は短くなる二季化についての解説が掲載されました。
・三重大学 生物資源学部のプレス発表
https://www.bio.mie-u.ac.jp/cate/happenings/92-5.html
・YahooJapanニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/712c9f142018335bb1528dbdf1655bcf99e5e9d4